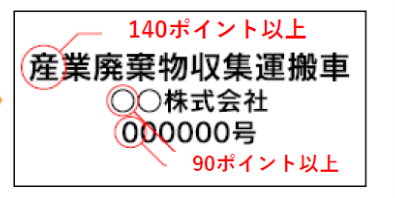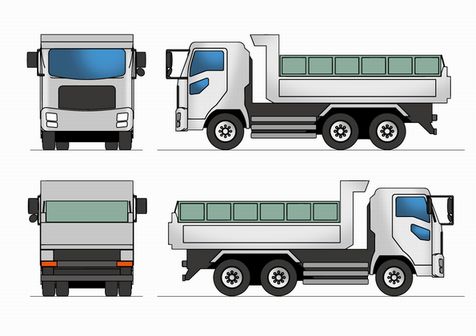| Q:産業廃棄物の中間処理施設を建設するには、事前に地元住民の同意を得ることが廃棄物処理法において義務付けられている? A:廃棄物処理法において中間処理施設の建設における住民の同意は義務ではない。 |
産業廃棄物の中間処理施設を建設するには、廃棄物処理法以外にも様々な法令が複雑に絡んできます。
産業廃棄物の中間処理を始める場合、廃棄物処理法において取得が必要な許可は、営業許可となる「産業廃棄物処分業許可」、設置する中間処理施設の内容によっては「産業廃棄物処理施設許可」です。
産業廃棄物処理施設は、全ての施設が許可対象となるわけではないことは過去のブログで解説しております。
2024年11月21日付「産業廃棄物処理施設を設置する際は、必ず許可を取得する必要がある?」
(産業廃棄物処理業)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
廃棄物処理法第14条
6 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
(産業廃棄物処理施設)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
廃棄物処理法第15条
産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
それでは、それぞれの許可を取得する際に地元住民の同意が必要か確認します。
まず、営業許可である産業廃棄物処分業の許可を取得する際に必要な書類は、廃棄物処理法施行規則第10条の4に記載がありますが、その中に地元住民の同意を求める書類はありません。
次に、施設許可については、以下条文に記載があります。
(産業廃棄物処理施設)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
廃棄物処理法第15条
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 産業廃棄物処理施設の種類
四 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
五 産業廃棄物処理施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
六 産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
八 産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画
九 その他環境省令で定める事項
3 前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該申請書に記載した同項第2号から第7号までに掲げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。
4 都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第2項第1号から第4号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第2項の申請書)を当該告示の日から1月間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該産業廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。
6 第4四項の規定による告示があつたときは、当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
産業廃棄物処分業の許可とは異なり、産業廃棄物処理施設を設置するには第15条第3項にとおり施設周辺に与える環境影響の調査書(生活環境影響調査書)を作成する必要があります。また、申請書及び生活環境影響調査書を誰でも見られるようにしなければなりません。
しかし、施設許可にも住民の同意を必要とする書類を求めていません。
中間処理施設を建設するには、都市計画法や建築基準法などの他法令により立地はある程度規制されるものの、このままでは急に住んでいる近くに施設が建設される可能性があります。

え!?このままだと住んでる近くに急に中間処理施設ができてしまうってこと・・・
たしかに突然住んでいる地域に中間処理施設が建設されたら周辺の住民は不安になることでしょう。
そこで、各都道府県では条例等を定め、廃棄物処理法の手続き前に周辺の住民や利害関係人に配慮することを義務付けています。
今回は、両筆者の元職場である「兵庫県」を例に解説します。
兵庫県では、【産業廃棄物処分業】、【産業廃棄物収集運搬業のうち積替保管を含むもの】を取得する際、事前に「産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防と調整に関する条例」によって地元調整を義務付けています。
簡単に条例の手続きを説明すると、施設設置を伴う産業廃棄物処理業の取得前に、事業者に対して地元住民に説明会等を実施させるとともに、地域住民の意向を踏まえつつ、必要に応じ、地元市町長への協力要請、紛争の斡旋、産業廃棄物審議会の意見聴取等を行うこととなっています。ただし、この条例においても地元住民の同意までを求めるものではありません。
条例において何を求めているかというと、地元住民との「合意形成」です。「同意」と「合意」で何が違うかというと、「同意」は、一方からの提案や意見に対して、相手が賛成や反対の意思を示すことを指しますが、「合意」は、複数の当事者が話し合いや交渉を経て、最終的に意見や認識を一致させることを意味します。
よって、「同意」を求めようとすると反対の意見が出た場合は断念せざるおえませんが、「合意」の場合は反対の理由をよく話し合って落としどころを見つけることになります。また、意見書に関しても施設設置に伴う環境への影響に関する意見に限っており、意見として反対を表明してもそれを基に手続きが滞ることはありません。
条例の趣旨は、周辺地域へ環境負荷の高い産業廃棄物処理施設ができることで与える影響を事前に考慮して周辺住民と十分に合意形成を行ってから事業を行って欲しい、というものです。
今回は兵庫県の条例について説明しましたが、各都道府県に廃棄物処理法の手続き前に事前条例や要綱が定められているはずですので、施設設置を伴う産廃処理業をお考えの方は、まず管轄自治体の手続きを確認しましょう。