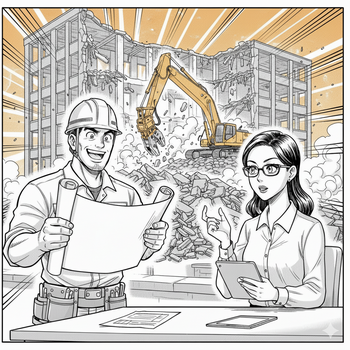| Q:解体工事の発注者は解体前の建物を所有していたため、解体後の廃棄物の排出事業者になっても良い? A:発注者ではなく、解体工事の元請業者が排出事業者になります。 |

建物だったときの所有者が排出事業者になった方が合理的じゃないの?
廃棄物処理法では、「建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外」として、
廃棄物処理法第21条の3
土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第3条第2項及び第3項、第4条第4項、第6条の3第2項及び第3項、第13条の12、第13条の13、第13条の15並びに第15条の7を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負つた建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。
と、「元請業者が建設廃棄物の排出事業者となる」規定を置いています。
発注者は、廃棄物処理法第21条の3でいうところの「建設工事の注文者」ですので、建設廃棄物の排出事業者には該当しないことがお分かりいただけると思います。
廃棄物処理法の中で、特定の業種を排出事業者として位置づけたのは、第21条の3の「元請業者」だけです。
発注者は解体工事が始まる前の建築物の所有者であったため、元々の所有物を解体後に発生した建築廃棄物の排出事業者になってもおかしくない感じはします。
しかしながら、廃棄物処理法の排出事業者には「処理責任」が必ず伴いますので、建設廃棄物の処理先を準備できない大部分の発注者を排出事業者として位置づけたとしても、建設廃棄物の円滑な処理が進むはずがありません。
そこで、廃棄物処理法では、「建設工事」という「事業活動」によって建設廃棄物を発生させた「元請業者」を排出事業者として位置づけることになりました。
ここで注意が必要な点は、
元請業者の建設工事で発生したわけではなく、発注者が解体対象の建築物に残した、あるいは放置した廃棄物(残置物)については、廃棄物処理法の原則どおり、発注者(注文者)が排出事業者となります。
残置物は、元請業者が建設工事で発生させたものではなく、発注者が排出事業者として処理責任を負うことになります。
残置物だけではなく、PCBが含まれる廃棄物についても、たとえそれが建設工事をきっかけとして処理する状況になったのだとしても、PCB特措法で
(事業者の責務)
第3条 保管事業者は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理しなければならない。
と、「保管事業者」すなわち「工事発注者(注文者)」が排出事業者として位置づけられていますので、やはり元請業者に処理責任が移転するわけではありません。
なお、PCB特措法では、
第2条第5項
「保管事業者」とは、その事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者をいう。
と定義していますので、上記の例の「工事発注者」を指しています。